- トップページ
- 機械工学科[機械A]紹介
機械工学科[機械A]紹介
DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING
[MECHANICAL A]

エネルギー・環境
×ロボット・モビリティ
×情報・デザイン
機械工学科は、
機械工学の視点で自然現象や社会事象の本質を理解し、
社会が求める新たな技術や価値の創造を探究し続けています。


モノに関する原理原則である“力学”と、
知識を統合しカタチにする“設計・生産”を基軸とする
機械工学は、産業革命以降、現在に至るまで、
モビリティのための自動車や航空機、
情報通信のためのスマートフォンなど、
人間が想像したもの、
想像すらしなかったものを実現し、
世界に変革をもたらしてきました。
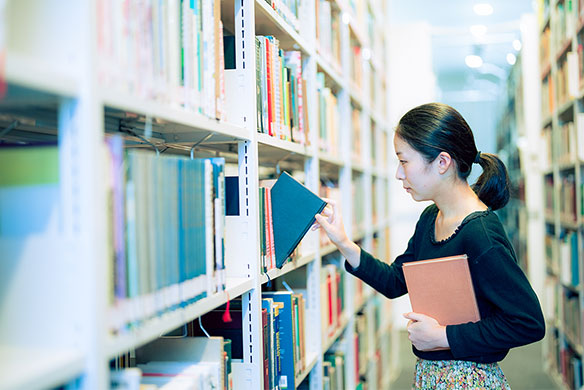


複雑化、多様化する社会において、
学生諸君が将来いかなる分野で、
いかなる物を対象に、
新たな創造を行う場合にも必要となる、
幅広い分野の基礎知識、技術、
それを融合する力を養えるよう、
研究を通じて自ら学ぶことができる場を、
機械工学科は提供します。





SDGs(Sustainable Development Goals、持続可能な開発目標)、
カーボンニュートラルなどの世界的課題の解決には、
物質、熱、流体、運動などで構成される物理現象を探究し、
人間の生活や社会のために最大限に活用することが不可欠です。



君たちが生きる豊かな未来の社会を創るのは、
君たち自身です。
機械工学科で身につけた、
技術・人間・社会・環境などの総合的な視野と
知の力で、新たな価値を創造しよう。



機械工学科プロモーションムービー(フルバージョン)
機械工学科の特徴
FEATURE
機械工学科/
機械工学専攻の歴史
HISTORY



機械工学専攻は、機械工学科が創設された1879年(明治12年)以来、機械工学分野に多くの人材を世に送り出しています。戦後の経済成長期にあって、機械系では主に、鉄道、自動車、造船、航空機、重機、電機、鉄鋼等各種プラントなど、我が国の基幹産業を創り支える技術者の育成を担ってきました。その後、産業界の分野の広がり、多様化の進展に対応すべく、教育、研究分野も変貌をとげつつあります。
例えば、生体工学、環境工学、分散エネルギーシステムの研究などは、時代の要請とともに広がってきた分野でありますし、分子熱工学、分子動力学などは現象解明の観点からマクロからミクロへと研究対象が移行して発生した分野であります。対象とする機械のスケールも、微細機械システムからインフラストラクチャーまで多様化しています。
機械工学専攻では、これらの研究分野の進展がカリキュラムにも反映されるよう、常に刷新して対応する努力が行われています。修士課程では産業界で広く活躍できる技術者の育成を、また博士課程では技術者として高度な専門的研究・開発に優れた能力を発揮できる人材の育成を目的としています。なお、教育、研究に関して生産技術研究所と協力する体制をとっています。
本郷の工学系研究科所属教員約40名、駒場第二キャンパスの生産技術研究所所属教員約15名が、協力して教育・研究にあたっています。



